【中国四大料理とは】広大な土地が育んだ多様な食文化を比べてみる
ホーム
生物・自然
【中国四大料理とは】広大な土地が育んだ多様な食文化を比べてみる
【中国四大料理とは】広大な土地が育んだ多様な食文化を比べてみる
生物・自然
2022.01.122020.06.16

ラビまる
一般に中国四大料理とは、「北京料理」「四川料理」「上海料理」「広東料理」のこと。
それぞれの料理体系を見ると、その土地の風土や文化をしっかりと反映していることがわかります。
中華料理は、いまや世界に広く普及している。
特に日本では、
「ランチはどうしよう。和・洋・中どれがいい?」
などというように、国内(和食)・国外(洋食)というかなりザックリした区分と並んで、「中華」が堂々と1つのジャンルとして選択肢に入ってくるほどだ。
しかし、とにかく広大な領土をもつ中国だから、その料理の特徴も「ズバリこれ」と絞れるようなものではなく、実際にはかなり多種多様に及ぶ。
そのなかでも中心となるものとして、俗に「中国四大料理」と呼ばれる料理の系統がある。
四大中国料理
日本では一般に次の4つを指す。
・【北方系】北京(ペキン)料理
・【西方系】四川(スーチョワン・しせん)料理
・【東方系】上海(シャンハイ)料理
・【南方系】広東(カントン)料理
これらは中国のそれぞれ異なる地域で発展してきた料理体系であり、面白いことに、いずれもその地域の風土を色濃く反映した特徴をもっているのである。
中国四大料理がどんなものなのか、順番に見ていこう。
厳しい環境に耐える!北方・西方系料理【北方系】北京料理
北京料理は、その名の通り中国全土の中でも北の方にある首都・北京を中心に発展した料理である。
もともとは「山東料理」といわれるもっと北方の地域の料理がルーツになっており、これが宮廷料理としてアレンジされていったのが今のカタチだと言われている。
このあたりの地域は畑作文化が根付いていたことから、麺類など小麦粉を使った料理が多い。
また北国の宿命でなんといっても冬が寒いので、脂肪やタンパク質をしっかりと補給すべく、豚・羊・アヒルを中心としたガッツリ系の肉料理がメインとなる。
味付けは、醤油や味噌、ショウガ、ニンニク、油がもりもりの、こってり濃いめの仕上がりである。
なんとなく体育会系なイメージですね。
こってり濃い味、肉と小麦の北京料理
【西方系】四川料理
四川料理は、中国の内陸部にある四川省のあたりで育まれた。
このエリアは四川盆地といって周囲を2000メートル級の山々に囲まれた地形をもっており、夏も冬もとにかく湿度が高くなりやすい。
高湿により食料がとても傷みやすく食中毒のリスクが大きいので、四川ではこれに対抗するため唐辛子や山椒などをふんだんに使った激辛料理が発展していった。
普通なら塩に漬け込んで保存食をつくるケースも多いけれども、残念ながら四川は海から遠く、おまけに高い山に阻まれているため交易ルートにも乏しい。
スパイスで料理を辛くすることが、彼らにとってベストな生活防衛策だったのである。
盆地では夏場はとても蒸し暑くなるから、夏バテ防止・健康維持の面でも、唐辛子たっぷりの四川料理が役立っていたと思われる。
スパイスの辛さが刺激的な四川料理
豊かな食材をいかした東方・南方系料理【東方系】上海料理
上海料理は、「江蘇料理」とよばれる長江流域の一帯で発展した料理体系をルーツにしている。
この辺りは中国有数の穀倉地帯であり稲作がたいへん盛んなので、コメの消費にマッチする「ごはんのおとも」的な料理が多い。
長江から豊富な淡水魚を確保できるだけでなく、東シナ海にも面しているため、エビ・カニなどの海産物を使ったものも多用される。
味付けは酒や醤油、黒酢といった醸造系の調味料を使うことが多く、濃厚な甘みがあることが特徴。
食材のレパートリーや味付けを考えると、結構日本人の食文化に近い料理といえるかもしれない。
ごはんがすすむ醤油味、上海料理
【南方系】広東料理
広東料理が発展した広州は、「食は広州にあり」といわれるほどの食の中心地である。
その特徴はなんと言っても食材の多様性。
東南アジアにも近いほどのかなり南方に位置するため、その温暖な気候から野菜やフルーツがよく獲れる。
また海にも面しているので、新鮮な海産物にも困らない。
加えて、広州に根付く強力なマインドとして、
「食べられるものは何でも食べる」
というのがあるらしく、ヘビ料理、イヌ料理、ネコ料理にいたるまで、なんでも来いの食文化である。
一方で味付けはシンプルで、極力素材の味をそのまま活かしたあっさりとしたものが多い。
いわゆるゲテモノ(良く言えば珍味)のことを考えると、「素材の味を活かす」という方針がいいのかどうかはちょっと判断に困るところである。
多彩な食材を楽しむ広東料理
「中華料理」といっても実はいろいろ
私たちが中華料理を語るときには、
「中華料理といえばフカヒレでしょ」
とか、
「辛いのが苦手だから中華料理は好きじゃないな」
とか、しばしば「中華料理」というジャンルを大きくひとまとめにしてくくってしまいがちである。
しかし実際は多種多様な個別の料理体系が歴史の中で複雑に絡み合って、総合していまの「中華料理」というおおまかな概念を形成している。
「珍味」とか「辛そう」とかそういったイメージは、その中のどれか特定の料理体系にあてはまるものでしかないのだ。
「中国四大料理」という区分だって決して絶対的なものではなくて、場合によってはもっと細分化して「中国八大料理」としたり、「中国十大料理」としたりすることもある。
当たり前のことだが「中国」というくくりはあくまで政治組織としての単位にすぎず、実際はその中にいろんな民族がいて、いろんな風土と文化が混在している。
それらをひとくくりにすることは、「イタリアン」や「フレンチ」をぜーんぶひっくるめて「洋食」と呼びまとめるのに負けず劣らず、テキトーな理解ということになるだろう。
普段何気なく口にしている中華料理も、それがどの系統から生まれたものなのかを意識してみると、より一層味わい深く感じられるかもしれない。
□【北方系】北京(ペキン)料理
・冬が寒い ⇒ こってり濃い味、肉料理
・畑作地域 ⇒ 小麦粉料理も多い
□【西方系】四川(スーチョワン・しせん)料理
・湿度が高い ⇒ 保存食&夏バテ防止の激辛料理
□【東方系】上海(シャンハイ)料理
・稲作地域 ⇒ コメに合う醤油ベースの料理
・海や川から魚が獲れる ⇒ 海鮮も多い
□【南方系】広東(カントン)料理
・温暖な気候 ⇒ 野菜やフルーツなど、食材豊富
・素材の味を活かしたシンプルな味付け
生物・自然
興味の窓メインコラム
シェアする
Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー
興味の窓 トップページへ
⇒身の回りの「おもしろい!」をコラムとして発信しています。
興味の窓
興味の窓
関連記事
科学・理論
【食用金箔の不思議】金箔って金属なのに食べちゃって大丈夫なの?
十分に基準を満たした食用の金箔は、食べても健康上まったく問題ないとされています。これに納得するために、金という元素がもつ性質について考えていきましょう。この記事の内容「金属は食べちゃいけない」という思い込みの解消金箔を食べても特に問題ない理...
生物・自然
キリンの名前の由来は、元をたどれば中国の霊獣「麒麟」にあった【鄭和の大航海】
動物のキリンは、伝説上の生物である麒麟にちなんでその名がつけられたとされています。今から約600年前の中国の故事が、時を経て現在の命名につながっているのです。キリンって、変わった見た目をしていますよね。動物の代表格だからもう慣れちゃったけど...
生物・自然
代表的なうま味成分とそれが多く含まれる食材をまとめて覚えよう
3つのうま味成分の特徴をわかりやすく表にしてまとめます。
生物・自然
「UNICUM(ウニクム)」のお味は?ハンガリーの養命酒とも称されるハーブリキュールを飲んでみる
ウニクムは健康酒としてハンガリーでは大人気。
とても苦いですが、ハンガリーの歴史と風土を感じながらほろ酔えます。
生物・自然
【ハニカム構造】コーヒーのおいしさを引き出す、焙煎豆の構造の秘密
新鮮な豆を使ってコーヒーを淹れると、粉がこんもりとドーム状に膨らんでいき、香り高いコーヒーが出来上がります。
この現象の鍵となるのは、コーヒー豆がもつ「ハニカム構造」です。(…続きを読む)
生物・自然
パッションフルーツの「パッション」、由来ってなんだろう
パッションフルーツは、香り高い南国のフルーツ。
その名前には、実はあのキリスト教が密接に関係していました。
(…続きを読む)
梶井基次郎「桜の樹の下には」のあらすじを簡単に解説
【バナナ型神話】人はなぜ死ぬ運命になったのか?世界各地の神話に共通するストーリーがある
コメント
コメントを書き込む
コメントをどうぞ
タグ一覧
興味の窓メインコラム50 まとめて知りたい教養5 〇〇の法則(定理3 〇〇現象(効果3 結局〇〇って何?3 語源5 お酒2 名作あらすじ3 認知心理学3 社会心理学2 学習心理学3 論理(数理)パズル3 生活を豊かに2
カテゴリー
パソコンで毎日決まった時間に音楽を自動再生して有意義な毎日を【Windowsタスクスケジューラ】
2020.08.152020.12.01
華氏って何を基準にしているの?温度の単位「摂氏」「華氏」の違いと、それぞれの良いところ悪いところ
2020.07.162020.07.16
絶対温度の単位「ケルビン」とは何か?定義が変更された意味までわかりやすく理解する【ボルツマン定数】
2020.07.212020.07.21
ヨットが逆風でも前に進める原理とは?【ベルヌーイの定理】
2020.04.042022.01.17
世界で唯一、日本語が「公用語」として定められている国を知っていますか?
2020.07.102022.01.17
最近の投稿その他

ラビまる
地方在住の好奇心旺盛な30歳。
大学時代の専攻は心理学で、今でも人文科学系の話題には興味シンシン。
読んでくれた方の興味が広がるきっかけとなるようなコラムを発信したいと思い、サイトを更新しています。
相关阅读
-

【中国四大料理とは】広大な土地が育んだ多様な食文化を比べてみる
ホーム生物・自然【中国四大料理とは】広大な土地が育んだ多様な食文化を比べてみる【中国四大料理とは】広大な土地が育んだ多様な食文化を比べてみる生物・自然2022.01...
-

1、我们先来看看社交问答平台,这种平台允许用户提问并由专家解答,平台从中获取收益,常见的问答形式包括C2C知识分享、积分制和招标悬赏等,虽然这种平台的参与门槛较低...
-

很多作者在选择sci期刊时会习惯性的根据其分值来看,比如最近不少人问的,10分左右的生物期刊哪些比较好?其实该方向期刊是在少数的,而且10分这一分值可以说是较高的了...
-

台湾首家纯电动车概念股,由鸿海科技集团(TWSE:2317)、裕隆集团(TWSE:2201)所合资成立的鸿华先进科技股份有限公司(TWSE:2258),今正式登创新板挂牌上市......
-
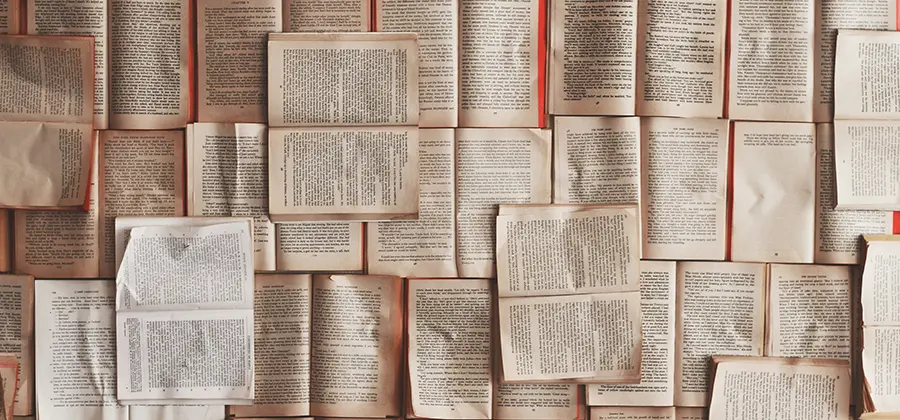
作者分享了关于知识付费和付费社群的20条心得体会,包括设置收费门槛、确定合适的价格、保证专业知识、及时变现、注重交付质量等方面,并提供了一些实用的建议和工具推荐。...
-

1、我们先来看看社交问答平台,这种平台允许用户提问并由专家解答,平台从中获取收益,常见的问答形式包括C2C知识分享、积分制和招标悬赏等,虽然这种平台的参与门槛较低...
-
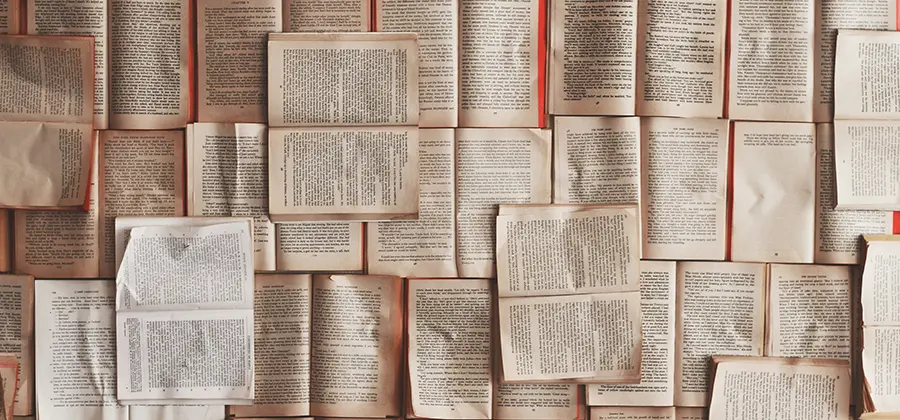
作者分享了关于知识付费和付费社群的20条心得体会,包括设置收费门槛、确定合适的价格、保证专业知识、及时变现、注重交付质量等方面,并提供了一些实用的建议和工具推荐。...
-
哪里有关于昆虫拟态的资料拟态http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ct=201326592&lm=-...
-

在现代社会,人们的生活节奏越来越快,工作与生活的压力也越来越大。然而,我们常常忽视了一个重要的因素,那就是规律的作息时间对于身体健康的重要性。...
-

科技创新要顶天立地...
-

2019年,中国知识付费行业用户规模达3.6亿人,行业市场规模达278.0亿元。...
发表评论
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。

